 取引先との契約書に、弊社が作成したWeb用の写真やデザインしたものについて、
取引先との契約書に、弊社が作成したWeb用の写真やデザインしたものについて、
「著作権の全部を譲渡する。」と記載があるのですが、よく意味がわかりません。
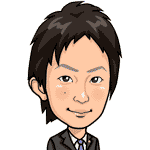 この質問について、IT事業に詳しい弁護士がお答えします。
この質問について、IT事業に詳しい弁護士がお答えします。
著作権とは
著作権とは、著作物を排他的に利用することができる財産的な権利のことをいいます。
これは、著作者がつくった著作物の財産的な価値を、著作者に固有のものとして保護の対象としたものといえます。
 たとえば、広告会社が作成した独自の写真やデザイン画は、その会社が作成したからこそ価値のあるものですので、勝手に流用されてしまうと、本来得るはずだった利益が得られなくなってしまいます。
たとえば、広告会社が作成した独自の写真やデザイン画は、その会社が作成したからこそ価値のあるものですので、勝手に流用されてしまうと、本来得るはずだった利益が得られなくなってしまいます。
そのため、著作者は「著作権」者として保護を受けることになります。
著作権侵害行為
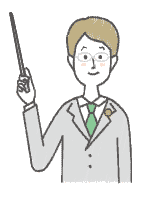 著作権を保護するために、著作権法は保護の対象を列挙しています(著作権法21条~28条)。
著作権を保護するために、著作権法は保護の対象を列挙しています(著作権法21条~28条)。
著作者の許諾なくこれらに該当する行為をしてしまうと、著作権侵害となり、損害賠償や差し止めの対象となります。
具体的には、以下の10の行為が対象です。
②上演権・演奏権(22条)
③上映権(22条の2)
④公衆送信権(送信可能化を含む、23条1項)
⑤口述権(24条)
⑥展示権(25条)
⑦頒布権(26条)
⑧譲渡権・貸与権(26条の2、26条の3)
⑨翻訳権・翻案権(27条)
⑩二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(28条)
著作権譲渡契約の締結
 ただし、著作権の譲渡契約を締結した場合は、著作権を譲り受けた者が著作権を保有するので、著作権侵害の問題が発生しにくくなります(後述しますが、著作者人格権を踏まえる必要があります。)。
ただし、著作権の譲渡契約を締結した場合は、著作権を譲り受けた者が著作権を保有するので、著作権侵害の問題が発生しにくくなります(後述しますが、著作者人格権を踏まえる必要があります。)。
そのため、著作権法上の権利として定められている権利の一切を譲渡するという趣旨で、「著作権の全部を譲渡する。」という文言が記載されるのです。
著作権法27条、28条について
 著作権譲渡契約においては、「著作権(以下、「本件著作権」という。なお、著作権法第27条及び第28条に規定されている権利を含む)の全部を譲渡する。」と記載されていることが多いと思います。
著作権譲渡契約においては、「著作権(以下、「本件著作権」という。なお、著作権法第27条及び第28条に規定されている権利を含む)の全部を譲渡する。」と記載されていることが多いと思います。
この27条、28条について説明します。
著作権法27条 翻訳権・翻案権
著作権法上の権利として(つまり、著作者の許諾なく行ってしまうと、著作権侵害となってしまう行為として)、第27条は、「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する」行為を挙げています。
この行為は、すでにある著作物に手を加えて、新たな著作物を生み出したり、創作的な変更を加えたりする行為のことを指します。
翻訳権、翻案権については、譲渡の際に明示しておかなければ、譲渡の対象とされません。
そのため、著作権譲渡契約において記載がされるのです。
著作権法28条 二次的著作物の利用に関する権利
著作権法上の権利として(くどいようですが、著作者の許諾なく行ってしまうと著作権侵害となってしまう行為として)、第28条は、著作物の「二次的著作物」が作成された場合に、それを利用する行為を挙げています。
ここで、「二次的著作物」とは、先ほどの翻訳、翻案行為によって生み出された新たな著作物のことをいいます(著作権法2条1項11号)。
つまり、二次的著作物の利用については、翻訳、翻案行為によって二次的著作物を作った者はもちろん、原著作者も保護されるので、許諾なき利用行為は原著作者に対する著作権侵害となります。
そのため、二次的著作物の利用に関する権利も、明示的に譲渡してもらわなければ、譲受人は困るわけです。
著作者人格権の不行使について
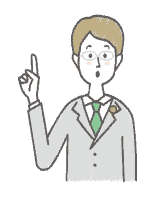 著作権譲渡契約においては、「著作者人格権の不行使」の記載もなされます。
著作権譲渡契約においては、「著作者人格権の不行使」の記載もなされます。
著作者人格権とは、著作者の人格的利益を保護する権利のことをいいます。
具体的には3つあり、
①公表権(自己の著作物を公表するか否か等を決定する権利)
②氏名表示権(自己の著作物に著作者名を付すか否か、どのような名義を付すかを決定する権利)
③同一性保持権(自己の著作物の内容や題号をその意に反して改変されない権利)
です。
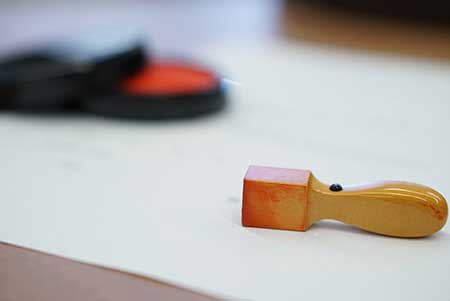
これらは、一身に専属する権利、つまり、著作者でも第三者に譲渡できない権利です(著作権法59条)。
そのため、著作権譲渡契約を締結したとしても、著作権侵害は起こり得るのです。
このような紛争を未然に防ぐために、「著作者人格権の不行使」を約束させるわけです。
著作権譲渡契約を締結するかどうか
 会社が作成した著作物の経済的価値は、本来的に会社に帰属すべきものです。つまり、著作物の価値は著作者が得るべきものです。
会社が作成した著作物の経済的価値は、本来的に会社に帰属すべきものです。つまり、著作物の価値は著作者が得るべきものです。
それを保持したいのであれば、著作権を譲渡すべきではありません。
著作物を相手方が利用したい場合は、著作物使用許諾契約を結ぶことによっても実現可能です。
取引におけるお互いのニーズはなにか、リスクはないか、あったとしても取るべきリスクなのか、まずはしっかり検討することが必要です。
お悩みの方は当事務所まで
 当事務所では、IT事業に特化した弁護士が対応しております。
当事務所では、IT事業に特化した弁護士が対応しております。
まずはお気軽に当事務所の弁護士までご相談ください。

